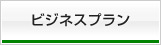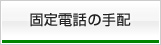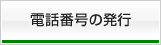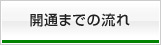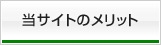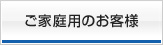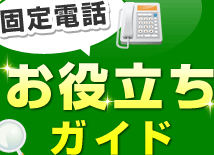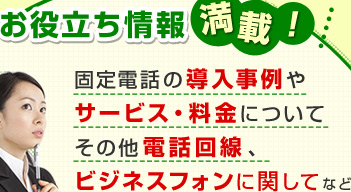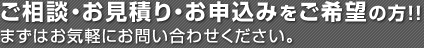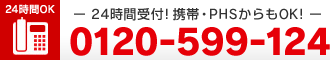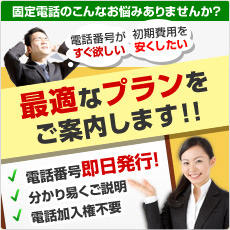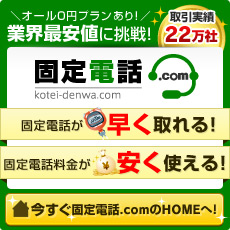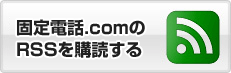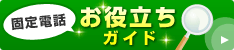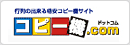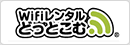【オフィス移転】アナログ回線に変更したい!

【オフィス移転】アナログ回線に変更したい!
オフィス移転が決まり、次なる電話回線がアナログ回線に決まっているという場合、どのような手順で行えばいいのでしょうか。例えば、これまでISDN回線を使用していた場合には、再構成が必要になります。また、アナログ回線に変更することにより、インターネット環境も変化します。
まだ移転先の回線が決まっていないという方も、アナログ回線にした場合、どんなことが必要になるのかをチェックしておくのをおすすめします。
オフィス移転時にアナログ回線にしたい場合
災害時などで、電力の供給がストップしてしまった場合、電話網は壊滅状態になります。そんなとき、アナログ回線は比較的つながるケースが多いといわれているため、ライフラインとして重宝されるケースが増えてきました。オフィス移転時にも、アナログ回線を検討される方は多いでしょう。
また、アナログ回線は、インターネット回線が不要な店舗や個人事業主などにも利用されています。同時通話数も1通話のみで十分、という業態であれば問題ないでしょう。
ISDN回線から変更する場合には注意が必要
オフィス移転後にアナログ回線を導入したいといっても、移転先の回線がISDN回線になっている可能性もあります。その場合には、アナログ回線への切り替えが必要になります。
また、移転前にISDN回線を使用していた場合も、ターミナルアダプタなどの機器は継続利用できなくなります。よく、ターミナルアダプタのアナログポートが使えるのではないかと思われる人もいるようですが、実際は使用できません。
ADSL回線の契約をしよう
電話をアナログ回線にすると、インターネット回線にはADSL回線を敷くことができます。
NTTのプランも、INSネット64か、INSネット64・ライトを使用していた場合には、アナログ回線の加入電話か加入電話・ライトプランに変更することで、ADSLを契約して利用できるようになります。
移転後、アナログ回線にしたいという場合には、移転先の回線状況を下調べすることから始めましょう!
【オフィス移転】同じ回線を使用したい!
【オフィス移転】同じ回線を使用したい!
急いでオフィス移転をしなくてはならなくなった場合、移転前のオフィスで使用していた電話回線と同じものを使用して、業務に支障が出ないようにしたいと考えるケースは少なくありません。しかし、移転先で万が一、同じ回線が使用できなかったときのことも考えておかなければなりません。
そこで、今回は、オフィス移転に際して、同じ回線を引き続き使用したいときの手順や確認方法などをご紹介します。
まずは今の環境を確認しよう
オフィス移転後も、同じ電話回線を使いたいという場合、まずは移転前の今使っている電話回線と通信機器を把握することから始めましょう。また、契約している回線数や利用会社、付加サービスがあればそれも確認が必要です。
電話回線はアナログ回線、ISDN回線、ひかり電話、IP電話の4種類が主流です。合わせて、インターネット回線はどの種類なのかの確認も必要です。
移転先で同じ回線が使えるかどうかを確認
今使っている回線が分かったら、同じものが移転先でも使えるかどうかを確認しましょう。また、電話番号の変更はなるべくであればしたくないものです。電話番号変更の必要があるかどうかも確認しておきましょう。
同じ回線が使えない場合、ビジネスフォンの機器も対応していないケースもあるので、そうなれば大変大掛かりな入れ替えとなります。どのようなケースにも対応できるように、できるだけ早めに確認しておくのをおすすめします。
特に光回線は調査が必要
光回線を使用する場合、建物によって状況が異なります。建物の室内に光ファイバーが引き込めるかどうかの確認が、NTTの担当者によって必要なこともあります。このMDF、IDF、配管などを確認する「下見」は、申し込んでから2週間程度の時間を要するので、よく注意が必要です。この下見の後、2週間程度後に工事が行われるのも想定しましょう。
オフィス移転の段取りは、このように早め早めに動くことが肝心です。何ごとも事前調査を欠かさずに余裕を持って行うのをおすすめします。
東日本大震災を経て見直された回線とは?

東日本大震災を経て見直された回線とは?
東日本大震災では、電話回線を巡って、ある事件が起きました。それは、アナログ回線が最も強く、つながりやすかったという内容です。
これは、携帯電話やIP電話という、日常的に最も普及していたものが、根底から覆された驚くべき事件でした。
東日本大震災ではアナログ回線が強かった
一時はもう終焉とすら思われていたアナログ回線でしたが、東日本大震災を経て、大きな変化がありました。なぜなら、携帯電話やIP電話と比べて、アナログ回線がつながりやすく、ライフラインとなりえたからでした。このことは、多くの人の常識を覆すことになったのです。震災後、アナログ回線を用意する人が、個人の家庭においても増えたといわれています。
IP電話はなぜ震災時NGに?
ところで、大震災の際、アナログ回線はなんとか電話通信がキープできたものの、IP電話やひかり電話は使えなくなった場所が多かったといわれています。その理由は、通信に光ファイバーを使っている点にあります。光ファイバーのインターネット回線は、電気を使用するため、停電時には通信が途絶えてしまいます。
銅の電話回線を利用しているアナログ回線は、この線の素材の理由から、インターネット回線よりも強い威力を発揮したのです。
携帯電話はなぜ震災時NGに?
大震災のとき、携帯電話もつながりにくい状況になりました。その理由は、携帯電話やPHS基地局の倒壊・流失などが主な原因です。通信事業社は、移動電源車や車載型携帯電話基地局を被災地に配置するなどして、通信サービスがいち早く復旧するよう取り組みました。
総務省によれば、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル、ウィルコムの5社の基地局が、合計で最大約29,000局が停波したといわれています。
普段の生活では気にも留めていないことでしたが、大震災時には、ライフラインとしての電話は非常に重要になります。日頃から、確実なライフラインを一つでも用意しておくことは必要不可欠といえそうです。
電話回線のケーブルの違い

電話回線のケーブルの違い
従来、電話回線といえば、銅線のアナログ回線だけでした。しかし、今では光ファイバーを使った回線など、さまざまなものが出てきていますよね。このような回線によって異なるケーブル事情を少し覗いてみましょう。
アナログ回線は銅線
色々な電話回線がある中で、古くからあるアナログ回線の通話をつなぐケーブルは、「銅線」です。メタル線とも呼ばれます。音声はこの銅線を通じて伝えられていきます。
この銅線の特徴は、まさに音声が銅線を伝わっていくことから、遠方になればなるほど音が弱くなっていくところです。音声がかすれたり、雑音が入ったりと、通話品質の面で懸念のあるところもあります。
現在では、高度な技術や設備が導入されており、通話品質はそれほど気にならなくなっていますが、基本的には他の回線と比べると劣ってしまうのは仕方がないようです。
ISDN回線も銅線
ISDN回線と呼ばれるのは、いわゆるデジタル回線のこと。アナログ回線と同じ銅線が使われています。アナログ回線は、直接音声を銅線に流していましたが、デジタル回線では、銅線にデジタル信号を流します。データを高速、かつノイズを避けて送ることができるので、アナログ回線よりもクリアな音声品質になります。
ひかり電話の光ファイバーはガラスorプラスチック
NTTのひかり電話でおなじみの光ファイバーを使った電話では、石英ガラスもしくはプラスチックの素材がケーブルに使われています。その構造は二重構造で、中心部に「コア」と呼ばれるものがあり、その周囲は「クラッド」と呼ばれるもので形成されています。
伝送は、電気信号をレーザー光へ変換し、高速で行うことが可能です。
ビジネスタイプでは、音声専用のIP網が構築され、通話帯域が確保されるので、従来の電話回線と堂々のクリアな音声品質での通話が可能になっています。
ケーブルの違いだけでなく、そのケーブルに何を通すかというところにも違いがあります。通話品質に深く関わることなので、ぜひ比較検討時にお役立てください。
NTTの電話回線種別一覧
NTTの電話回線種別一覧
NTTの電話回線種別には、現在、5種類あります。この5種類の電話回線はどのように選び分ければいいのでしょうか。そのサービスの違いを見てみることにしましょう。
NTTの電話回線種別には何がある?
NTTの電話回線種別には、「加入電話」「加入電話・ライトプラン」「INSネット64」「INSネット64・ライト」「ひかり電話」の5種類があります。この5種類のうち、「加入電話」とついているものは、アナログ回線で、「INSネット」とついているものはデジタル回線になります。また「ライト」とついているものと「ひかり電話」は、施設設置負担金が不要のサービスです。
加入電話、加入電話・ライトプラン
加入電話と、加入電話・ライトプランは、どちらもアナログ回線の電話となります。サービス内容には違いがありませんが、初期費用が異なります。
加入電話は、施設設置負担金が36,000円(税抜)かかりますが、加入電話・ライトプランでは不要です。どちらも契約料800円(税抜)がかかりますが、その他、月々にかかる費用は、加入電話・ライトプランのほうが少し割高になります。
どちらもプッシュ回線とダイヤル回線の2種類があります。インターネットをしたい場合、ADSL回線を利用することができます。
INSネット64、INSネット64・ライト
INSネット64とINSネット64・ライトは、どちらもデジタル回線の電話です。ビジネス利用でも便利なのは、1本で2回線使用できることです。サービス内容はどちらも同じですが、INSネット64のほうは施設設置負担金がかかります。しかし、月々の使用料金はINSネット64・ライトのほうが少々割高になります。
どちらもフレッツ・ISDNを契約することで、インターネットが定額で利用できます。
ひかり電話
光ファイバーを使用したインターネット接続サービスである「フレッツ光」を契約すると、利用できるようになる光IP電話です。通話品質も劣らず、他サービスと比べて基本料金が安く、電話番号も電話機も従来のものが使用できます。
そのお得さが受けており、ビジネスシーンでも多く導入されています。