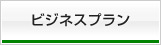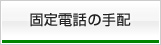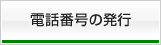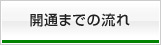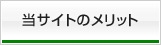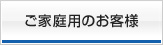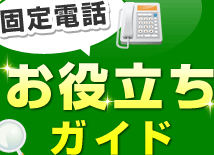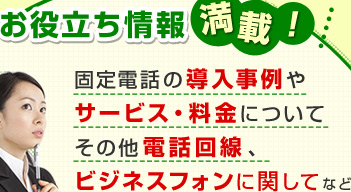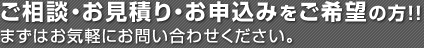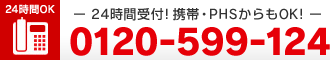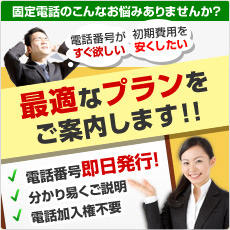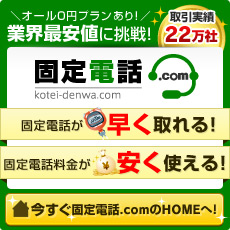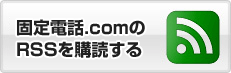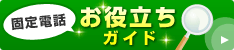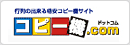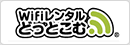IPネットワークの仕組みを知ろう

IPネットワークの仕組みを知ろう
IP電話といえば、インターネットなどのIPネットワークによって実現される電話です。みなさん、なんとなくどのようなものなのかはイメージがつくことでしょう。このIP電話を理解するには、基盤の技術である「VoIP」というものを知ることが重要になってきます。
そこで、今回はIP電話のIPネットワークの仕組みについて見てみましょう。
■IP電話のネットワーク
IP電話に欠かせない「VoIP」とは、「Voice over IP」の略称で、IPネットワークを介して、音声をやり取りすることによって電話が成り立つ技術です。
IPネットワークにおいては、音声がIPパケットに変換されて通話の相手に送信されます。IPパケットを作るには、音声をデジタル信号に変換する必要があります。このデジタル信号に変換してパケットをつくりだすのが「VoIPゲートウェイ」と呼ばれる装置です。これによって、従来の電話機でもIP電話が使えるようになります。
■電話網IPネットワークを介する電話が実現仕組みとは?
VoIPゲートウェイは、インターネットや社内のイントラネットなどで、社内の電話網を構築します。
VoIPの仕組みとしては、まず電話線からやってくるアナログの音声データをデジタルデータに変換します。それをIPパケットに分割することで、IPネットワーク上に送信します。そして同時に次のことを行います。
それは、IPネットワークのほうからも、IPパケットを受け取ってアナログ音声に復元することです。こうして復元したアナログ音声は、電話網へ送り出されるのです。
このようなVoIPゲートウェイを使う仕組みは、すでにシステムが構築されているものがサービス提供されていることもあり、企業は比較的容易にIP電話ネットワークを構築することができるようになっています。
もしIP電話を導入したい場合には、この仕組みを簡単にでも理解しておけば、どのような機器がどのような働きをしているのかを知ることができるので、不具合が起きた場合も対処がしやすいでしょう。
電話回線とは?

今日は電話回線の種類について簡単に説明したいと思います。
電話回線は大きく分けて【アナログ回線】【ISDN】と【光ファイバー】の3種類があります。
【アナログ回線とは?】
インターネットの普及以前からある電話回線で、一般的な電話回線というと、少し前まではアナログ回線のことでした。黒電話時代から始まって今でも利用されています。回線自体は銅で出来ています。
【ISDN回線とは?】
ISDN回線とは、アナログ回線と同様の導線を利用し、その回線に対してデジタル信号を流す回線方法です。
簡単にいうと、いったん音声情報を「0」と「1」のデジタル信号に変換し、それが導線内を伝わっていきます。
ISDN回線のメリットとしては、音声情報をデジタル化することで、情報量を少なくできるので、音質は綺麗になり、しかも、電話線1本に対し2回線分の利用ができるのが特徴です。
家庭では、インターネットと電話。法人では、FAXと電話回線として利用されることが多いようです。
【光ファイバーとは?】
光ファイバーとは、ガラス線の中を光の点滅を利用して、情報が伝わっていきます。
光なので、一度に送れる通信料は多いのですが、まだ回線が不安定になったりと課題を抱えているのも事実。
法人であれば、ISDN回線と光ファイバーを上手く利用して通信環境を整えたいですね。
ひかり電話とは??

ひかり電話とは??
ひかり電話とは、NTT東日本、西日本が提供する光ファイバー通信サービス「フレッツ光」を利用した光IP電話サービスの商品名です
(光IP電話とは光回線を利用したIP電話の事です)
メタル回線(電話線)を引かなくてもインターネット接続サービスと一般電話サービスの両方を受けられます。
他のIP電話サービスと違い・・
・03-XXXX-XXXXなどのIP電話番号が使える
・今使っている固定電話番号をそのまま使える
・電話機もそのまま使うことが出来る
・110番、119番などの緊急電話もかけることが可能
・オプションサービスも充実
音質は従来の固定電話並みに良いんです!
ひかり電話は総務省が定める基準に則り、固定電話相当の品質を確保しており、
厳しい基準を設けることで、0AB~Jの番号を利用する電話サービス(従来の固定電話)の品質を保っています。
固定電話とは??

固定電話(こていでんわ)とは?
携帯電話やPHSのような移動式電話、公衆電話以外の電話のことです。
有線加入電話、IP電話などが固定電話にあたります。
携帯電話が出てきたことで、それに対する言葉として生み出された用語で、「家電話」「家電(イエデン)」と呼ばれることもあります。
固定電話は設置場所が電気通信事業者により特定され、警察・消防当局はそれぞれの緊急番号である110番受報、119番受報でその場所を知る事ができます。
貸金業者は貸金業法の規定により、貸金業登録簿に記載できる電話番号は固定電話だけ。
公衆電話同様、携帯電話が普及したこと、それにインターネット接続を固定電話契約なしでも行うことが可能となったことで、現在ではその契約数が減少している。
ピークの1997年11月には6322万回線が存在したが、2011年12月には3600万回線程度まで減少した(ただしIP電話に置き換わったものもあり、こちらの同月における番号利用数は約2700万回線である)。
昔は電話加入の時に高額な加入権料(施設設置負担金)を支払う必要がありました
最近ではNTT以外の企業が固定電話に参入したり、IP電話が普及したりしたことにより、負担金なしでも固定回線を引くことができるようになりました。
電話の移転後もビジネスフォンは配線・設定が必要

電話の移転後もビジネスフォンは配線・設定が必要
オフィスの移転などで、電話回線の手配や準備が済み、いよいよビジネスフォンを導入するシーンが訪れました。さて、実際どうやって配線と設定をすればいいのでしょうか。
配線と設定は業者に一任しているという場合も、しくみを理解しておくと何かと役立ちます。そこで、オフィス移転時などにビジネスフォンを設置する方法を紹介します。
■オフィス移転!回線は変更なし そのままつなげる?
オフィス移転の際に、電話の接続はビジネスフォンにモジュラージャックをつなぐだけで済むだろうと思っている方はいませんか? 実は、家庭電話とは異なり、ビジネスフォンは少々事情が異なるのです。ビジネスフォンには、主装置と呼ばれる機器と電話機を接続する必要があるのです。まずは主装置を設置してから、そこにビジネスフォンをつなげるというのが通例です。
■ビジネスフォンの主装置の設置場所を決める
ビジネスフォン環境の構築には、主装置の設置が必要不可欠であることが分かりました。そこで、まずは主装置の設置場所を考える必要があります。電源があることはもちろん必要ですが、主装置は普段目に見えないところに置いておくのがいいでしょう。直射日光が当たる場所もNGなので、よく考えて設置場所を決める必要があります。
■主装置や配線などを専門業者に依頼しよう
主装置の場所が決まったら、実際の配線などは、専門業者にお願いするのが一般的です。電話機がつながれれば、今度は各電話機の内線番号などのデータ設定を行います。
オフィス移転時には専門業者に依頼して色々と行うことも多いですが、主装置や電話機の場所などは、随時指定していきたいものです。そのためにも、ビジネスフォンの設定方法や、配線のしくみなどはぜひ心得ておくのをおすすめします。
もし配線がむずかしいなどの不具合などが起きた場合でも、理解が早いからです。ぜひ事前に知識を持って、オフィス移転、電話移設に取り組むのをおすすめします。